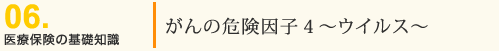
ウィルスは、細胞を侵し、遺伝物質を変化させる性質をもっているため、いくつかのがんは、ウィルス感染に関係しています。
胃がん: ピロリ菌
胃がんの危険因子は、主に胃粘膜の老化と食生活ですが、最近はヘリコバクターピロリ菌との関係も指摘されています。
ピロリ菌が胃粘膜障害の初期および慢性萎縮性胃炎の進展に関与していること、および分化型がん患者の90%、未分化型がん患者でも過半数にピロリ菌の感染が見られたことなどによって胃がんとピロリ菌の関連が分かってきました。
子宮頸がん: ヒトパピローマウイルス
子宮頸がんは40歳以上では年々減少していますが、20〜30歳代の若年層では年々増加しています。子宮頸がんの発生の多くには、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が関連しています。子宮頸がんの患者さんの90%以上からHPVが検出されていることが知られていますが、HPVに感染すること自体はけっして特別なことではありません。性交経験がある女性であれば、誰でも感染する可能性があるのです。
子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)は、子宮頸がん全体の60〜70%の原因であるHPV16型・18型の2種類の感染予防を目的としています。欧米をはじめとする世界100カ国以上で発売されており、日本でも2009年10月に承認され、同年12月から接種できるようになりました。
ワクチンの効果と、最新の日本人の疫学報告および子宮頸がんの年齢分布を照らし合わせると、ワクチンによってすべての子宮頸がんの発症数を約70%減少すると推計されています。
肝がん: 肝炎ウイルス
B型肝炎・C型肝炎ウイルスは、世界中で多くの人の死因となっている肝がんの多くに関連しています。
日本人の場合、最初から肝臓にできるがん(原発肝がん)の大半を占める肝細胞がんは、そのほとんどが肝硬変または慢性肝炎のある肝臓に発生し、肝がんにかかる人の16%がB型肝炎ウイルスに、76%がC型肝炎ウイルスに感染(重複もあり)していたという報告もあります。
これらの人は、慢性肝炎→肝硬変→肝細胞がんへという経過をたどるわけです。
<B型肝炎・C型肝炎ウイルスの感染経路> 飯野四郎著「ウイルス感染・2」より
| |
B型肝炎 |
C型肝炎 |
輸血・血液製剤
による感染 |
以前はあり。
1990年以降、ほぼ消滅 |
以前はあり。
1992年以降、ほぼ消滅 |
汚染血液や
傷の血液など
からの感染 |
あり。注射器、鍼治療、入れ墨などの医療事故などで見られる。 |
あり。注射器、鍼治療、入れ墨などの医療事故などで見られる。 |
母子感染 |
あり。1986年から防止事業が始まり、現在ではほぼ消滅 |
約2%。
経過観察が必要 |
性行為感染 |
あり |
ごくまれ |
通常の日常生活 |
なし |
なし |
白血病: ヒトT細胞白血病ウイルス・タイプI(HTLV-I)
白血病にはいくつか種類がありますが、リンパ系の白血病である成人T細胞白血病(ATL)は、その発症にヒトT細胞白血病ウイルス・タイプⅠ(HTLV-Ⅰ)が強く関係していると考えられています。
成人T細胞白血病(ATL)は、1977年(昭和52)に日本で発見された、変わった形をもつリンパ系の白血病で、九州、四国南部、紀伊半島に多く患者が出ています。
ATLウイルスの感染力は弱く、感染には、
(1)輸血による感染
(2)性交による感染
(3)母乳による感染
の三つの経路しかありません。
2004.8.22記事 2011.3更新 |