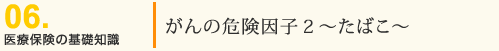
たばこを吸う習慣は、世界のどこの国においても、肺がんの主な原因となっています。
そればかりか、自分はたばこを吸わないのに、喫煙者の周囲にいて煙を吸う人(受動喫煙者)にも、発がんの危険性を高めます。
たばこを吸う人は吸わない人の4倍以上も肺がんになりやすく、そのリスクは、1日に吸う本数と、喫煙年数に比例して大きくなります(平山 雄 元国立がんセンター研究所疫学部長)。
肺がんは、すべてのがんの中でも近年、男女共に急激に増えているがんで、日本人のがんによる死の1位です。
また、咽頭がんは肺がん以上にたばこの影響を受け、咽頭がん、口腔がん、胃がん、食道がん、腎臓がん、膀胱がん、膵がんなどの発生率も、喫煙者の方がたばこを吸わない人よりもはるかに高くなっています。
このように多くの種類のがんの大半を、たばこを吸わないことによって防ぐことができるのです。
しかし、喫煙をすればがんや心臓病、肺の病気になる危険性は減りますが、喫煙歴が20年を超えてしまうと、喫煙しても喫煙習慣が全くない人と危険性が同じということにはなりません。
現在は、肺がんは男性に多く、女性の3倍に達しています。
しかし、最近では男性の喫煙率は減っているのに女性の喫煙率が増えていて、その結果ががんとなって現れる10年、20年後の女性の肺がんの増加が心配されています。
しかも、女性の方がたばこの影響は大きいというデータもありますから、男性より少ない本数でも、がんの危険性は高いといえそうです。
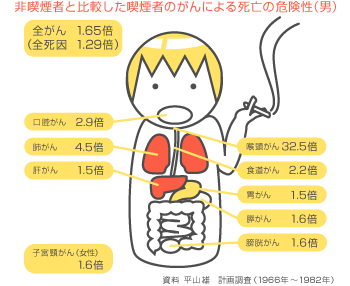
2004.8.8記事 2007.7更新 |