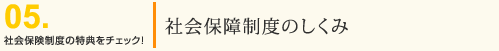
保険加入や保険の見直しの際、必要保障額を算出することは重要です。
その際、支出見込みのすべての金額を自助努力で補うということではなく、収入見込みの1つとして社会保障制度を活用して補うことができるということを忘れてはいけません。
今回は、日本の社会保障制度について勉強していきましょう。
日本の社会保障制度は、「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「公衆衛生及び医療」の4つの分野で成り立っています。
このうち、社会保険以外は国の財源のみにより国民に提供されるものです。
4つの社会保障制度の中で、保険加入や保険見直しの際に最も密接なかかわりをもつのは、年金保険や医療保険、介護保険などの「社会保険」です。社会保険は、国民に加入を義務づけて保険料を徴収し、病気や老後、介護などの場合に国(介護保険の場合は市区町村)が一定の給付を行う、いわば助け合いにより成り立っている制度です。
ただし、「社会保険」は、財源のすべてを国民から徴収している保険料に負っているわけではなく、租税財源による国や地方自治体の負担分も少なくありません。
そこで、日本の少子高齢化の問題が今後一段と進んでいくと、国民所得に対する租税・社会保険料の割合を示す「国民負担率」の上昇を招くこととなり、社会保険の給付と負担のバランスが崩れていくと予想されます。
国や企業に社会保障の全てを依存する時代は完全に終わりました。
社会保障制度をうまく取り入れた自助努力をしていくことが大切です。
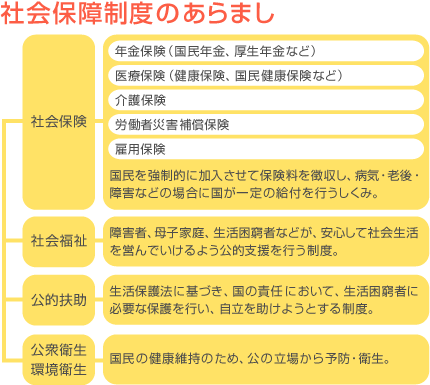
2004.10.3記事 2007.7更新 |