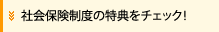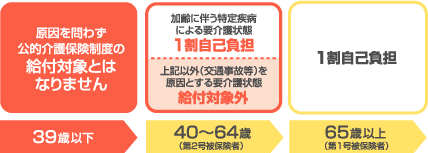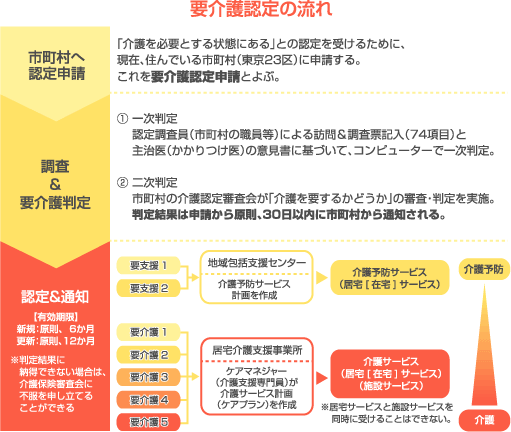|
|
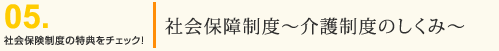
公的介護保険とは、日本で2000年4月にスタートした制度で、40歳以上の国民全員が加入し、介護サービスを受けることができます。社会保障制度には、年金制度や医療制度がありますが、これらが「現金給付」という点に対して、介護制度は、要介護認定を受けた利用者が所得にかかわらず1割の利用料を支払うことで介護サービスそのものが給付される「現物給付」となっている点が他の制度との大きな違いです。
介護保険が利用できる人公的介護保険は、65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の2つに大別されますが、いずれの制度も私たちが負担する保険料によって運営されています。
介護保険の給付の仕組みと流れ介護保険制度の運営は市町村(東京23区)が行っています。介護保険のサービスを受けるためには、現在住んでいる市町村に申請して、要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。申請を受けた市町村では申請にもとづいて認定調査を行い、要介護・要支援に該当するかどうかを決定します。
ここで「非該当」とされた人は介護保険によるサービスを受けることはできません(市町村などが行う介護予防サービスは受けることができます)。介護を必要とする度合いに応じて、「要支援1〜2」と「要介護1〜5」の7段階に認定されます。 要支援、要介護度区分ごとの介護を受ける人の状態と支給限度額要介護の認定を受けた人は介護給付、要支援の認定を受けた人は予防給付を利用することができます。これらの給付を受ける場合は、原則として利用した介護サービスの1割を自己負担しなければなりません。また、各段階ごとに介護サービスの支給限度額を定めていますが、限度額を超えた場合には、超えた分について全額自己負担となります。 認定区分と支給限度額
<出典:生命保険文化センター「介護保障ガイド」> ※支給限度額は標準的な地域のケース。大都市の場合、介護サービスの内容に応じて、利用料が10.5%高くなるため、支給限度額は表中の数値と異なる場合がある。 介護サービスの種類要介護の認定を受けた人はケアマネージャーが介護サービス計画を、要支援の認定を受けた人は保健師等が介護予防サービス計画を、いずれも無料で作成してくれます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
内容 |
サービス費用 (10割) |
利用者負担 (1割) |
訪問介護 |
介護福祉士やホームヘルパーの訪問 例)身体介護(1時間未満) |
4,020円 |
402円 |
訪問入浴介護 |
介護職員と看護師が移動入浴車などで訪問 例)全身浴(1回あたり) |
12,500円 |
1,250円 |
訪問看護 |
看護師などの訪問 例)訪問看護ステーション (1時間未満) |
8,300円 |
830円 |
訪問リハビリテーション |
リハビリの専門職の訪問 例)訪問(1回あたり) |
3,050円 |
305円 |
居宅療養 管理指導 |
医師・歯科医・薬剤師・栄養士・歯科衛生士による指導 例)医師・歯科医師(月2回まで) |
5,000円 |
500円 |
 施設などを利用して受けるサービス
施設などを利用して受けるサービス
項目 |
内容 |
サービス費用 (10割) |
利用者負担 (1割) |
通所介護 (デイサービス) |
日帰り介護施設への通所 例)要介護5(1回あたり:6時間以上8時間未満の場合) |
6,770円 |
677円 |
通所 リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設や病院・診療所への通所 例)要介護5(1回あたり:6時間以上8時間未満の場合) |
13,030円 |
1,303円 |
短期入所生活介護 (福祉施設でのショートステイ) |
特別養護老人ホームや老人福祉施設などへの短期入所 例)要介護5(1日あたり・相部屋) |
10,190円 |
1,019円 |
夜間対応型 訪問介護 |
夜間の巡回や通報システムにより対応する訪問介護 例)基本月額 |
10,000円 |
1,000円 |
地域密着型 特定施設入居者 生活介護 |
有料老人ホームなどでの介護 例)要介護5(1日あたり) |
8,510円 |
851円 |
 介護環境を整えるサービス
介護環境を整えるサービス
- 福祉用具の貸与:車いす・特殊寝台などの貸与
- 福祉用具の購入費支給:腰掛け便座・入浴用いすなど
- 住宅改装費の支給:手すりの取付け、段差の解消など
 施設サービス
施設サービス
施設サービスを利用できるのは、要介護1から要介護5と認定された人です。
申込みは各施設に直接行いますが、いずれの施設も入所待ちの人が大変多く、なかなか入所できないのが現状です。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院など)
介護保険施設に入所した場合の負担額は、以下の合計額となります。
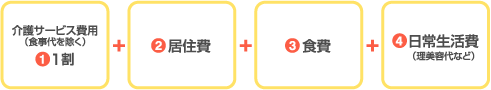
高額介護サービス費
サービス利用料の1割を自己負担する介護保険制度では、その負担によって利用者自身が介護サービスを抑制したり、利用料を払えない人をサービス提供者が拒否するなどの問題が予想され、自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、申請すれば超えた分が払い戻されます。申請は、各市町村に領収書、高額介護サービス費支給申請書などを提出します。
対象 |
上限額 |
一 般 |
37,200円 |
住民税非課税世帯 |
24,600円 |
住民税非課税世帯で、本人の合計 所得および年金収入の合計が80万円以下 |
15,000円 |
生活保護の受給者、 住民税世帯非課税で老齢者福祉年金受給者 |
15,000円 |
なお、医療保険においても一定の限度額を超えた部分は支給される「高額療養費」の制度があります。そのため、平成20年4月より介護保険、医療保険の自己負担の合計額が高額になった場合には「高額介護合算療養費」として限度額を超えた部分が支給される制度が新設されています。
介護合算算定基準額
70歳以上75歳未満の人 のみの世帯 |
70歳未満の人を含む世帯 |
|
上位所得者 (現役並み所得者)※1 |
67万円 |
126万円 |
一般 |
56万円 |
67万円 |
低所得者II ※2 |
31万円 |
34万円 |
低所得者II ※3 |
19万円 |
34万円 |
※1 上位所得者とは:月収53万円以上(自営業の場合は総所得金額が600万円超)の人
現役並み所得者とは:月収28万円以上(会社員の場合)または課税所得145万円以
上で、夫婦2人世帯で年収約520万円以上、単身世帯で年収約380万円以上の人
※2 低所得者Ⅱとは:世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である人
※3 低所得者Ⅰとは:世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差引いたときに0円となる人
 |
|
|
2000年4月から導入された公的介護保険制度ですが、介護認定者数は厚生労働省の予想をはるかに上回る速さで増え続けています。団塊世代といわれる人たちが、今後65歳以上の高齢期に入っていくなか、介護給付費の増大は避けられません。 |
|