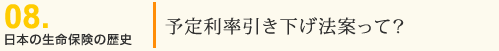
さて、加入している保険の契約年度、そして予定利率を確認しましたか?
今回の保険ゼミでは、1995年(平成7年)以前に契約した保険に加入しているあなたへのアドバイスです。予定利率引下げ法案に関係があるからです。
1996年(平成8年)以降に契約したあなたは、周りの方にアドバイスできるようにさらっと学んでくださいね。
2003年6月、生命保険会社が破綻する前に予定利率を引き下げることができる保険業法改正案が国会で可決されました。
これを「予定利率引下げ法案」と一般的に呼んでいます。
実際どのようにして、「予定利率引下げ」を実行するのでしょう。
保険会社が勝手に実行することはできず、契約者の同意が必要になります。
以下のプロセスで実行されます。
もう破綻しそうだと自主判断した保険会社が政府に申請後、
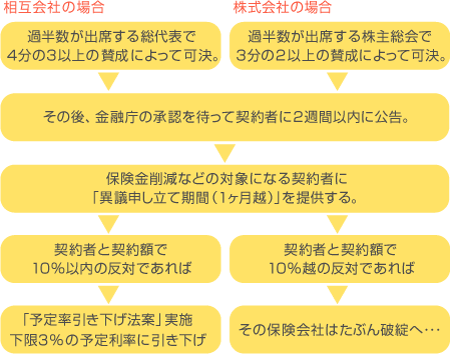
予定利率の引き下げが認められるのは、経営難の生命保険会社だけで、過半数が出席する総代会、もしくは株主総会では4分の3以上の賛成が必要ですし、予定利率の引き上げも3%を下限としています。
では、実際に予定利率が引き下げになるとどのような影響があるのでしょうか?
保険料に変更がなければ、契約している保険金額が減ることとなります。
特に、養老保険や終身保険、長期の定期保険などの貯蓄性がある商品に加入している人の減額幅は大きく、金融庁が以下のようなシュミレーションを発表しています。
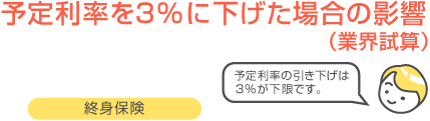
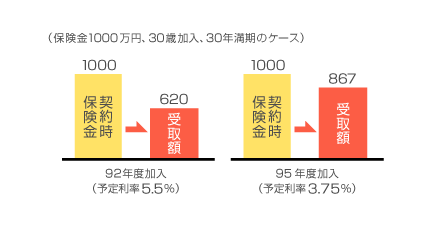
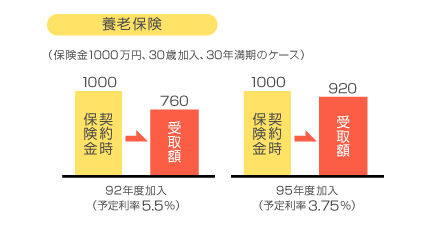
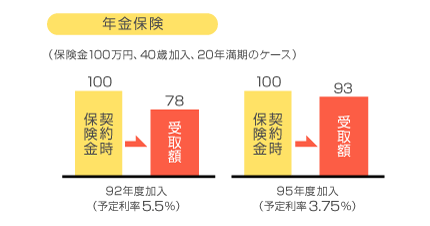
保険の種類、加入年齢によっても影響の度合いがかなり異なっていることに注目してください。
もっとも影響を受けるのは終身保険、次に影響が大きいのが養老保険と年金保険です。
いずれも貯蓄型の生命保険で、期間が長いものほど影響が大きくなります。
影響が少ないのは、定期保険のようなかけ捨て型の保険です。
定期付終身保険の場合は、定期(かけ捨て)と終身(貯蓄)の割合によって影響度が違ってきます。
すでに、高い予定利率の契約が保険会社の経営を圧迫していることから、万が一破綻するくらいであれば、高い予定利率の契約者に犠牲になってもらうかも、ということで「予定利率引下げ法案」で保険業法を改正し、いざというときは、保険金額を減額して支払うことによって、経営悪化を改善するということを逃げ道として考えています。
さて、加入している生命保険の予定利率が引き下げることになったら、どのように対処すればよいでしょうか?
予定利率が引き下げられても、3%は保証されますので、今の保険の予定利率1.5%よりは高いものになります。
今加入している生命保険を解約して、新しい生命保険に加入しようとすると、病気にかかっていて加入できない、年齢が高くなっているので、加入しなおしたほうが保険料が高くなってしまうというケースも考えられます。あわてて解約することのないように、十分な注意が必要です。
2004.5.23記事 2007.7更新 |