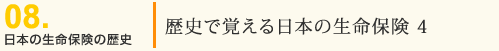
日本における保険種類の歴史的推移を保有契約高で見ると、最初は終身保険が大半を占めていましたが、だんだんと終身保険が減少して養老保険が保険契約の主流を占めるようになりました。
簡単に遍歴をまとめると、
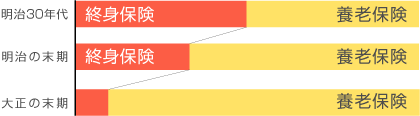
明治30年代・・・養老保険と終身保険は1/2ずつの割合
明治の末期・・・終身保険は1/3に減少
大正の末期・・・終身保険は1割弱→昭和20年代まで状況変化なし
このように、終身保険が減少して養老保険が保険契約の主流を占めるようになったのは、養老保険が持つ貯蓄機能がより高く評価され、一方で、より多くの保障機能を持っている終身保険に対する需要が少なかったからです。
その理由としては、
 その1 その1 |
| |
家族制度や家業の世襲制を中心とする生活保障制度や封建的な慣習やものの考え方が強く残っており、独立した近代市民としての生活と思想が確立されていなかったこと。 |
 その2 その2 |
| |
死に対する因習縁起が残っていて、死亡保障について割り切った考え方が持ちにくかったこと。 |
 その3 その3 |
| |
伝統的に貯蓄思想が強かったこと。 |
が挙げられます。
さらに保険会社として、これらの考え方に対応して理解されやすい養老保険に主力をおいた募集政策を採っていたことも、一つの要因と考えられています。
昭和16年、第二次大戦に突入するに伴い、あらゆる産業、金融、教育機関などはすべて厳しい戦時体制下におかれました。
生命保険会社も大量の国債引受や、軍事産業への投資を強いられることとなったのです。
また、政府は戦時財政上、統制経済を強化するとともに、消費を抑えるために「国民貯蓄奨励運動」を行いましたが、「国民貯蓄は生命保険から」などのスローガンのもとに生命保険会社も政府に協力していったのです。
昭和20年8月15日、日本は無条件降伏をして、第二次世界大戦は終了しました。
敗戦後の経済インフレーションは、急速に進み、生命保険会社も大きな痛手を受けたのです。
このため、昭和21年、金融機関再建整備法により、生命保険会社の資産・負債が新・旧勘定に分離され、旧勘定を整理の対象とするとともに、新勘定で再建整備を行うことになりました。
この際、多くの会社が新旧勘定を吸収するための第二会社を設立し、再出発を図ることとなりました。
この第二会社設立に際し、多くの会社が株式会社から相互会社へと組織変更したのです。
敗戦による国民所得の低下により、保険料負担能力は弱まり、年払、半年払に限っていた民間の生命保険会社の新契約は著しく低下していきました。
こういった状況の中で、小口の集金を伴う月払いの生命保険は、戦前、簡易生命保険法により官営の独占事業とされていましたが、昭和21年に同法が改正され、民間の生命保険会社でも取り扱うことができるようになりました。
昭和24年以降、多くの保険会社がこの分野に進出して、再建の第一歩を踏み出したのです。
この月払保険では、営業職員が一定の担当地区を持ち、その地区内の新契約の募集と募金活動を並行して行うデビット・システムと呼ばれる方法が導入されました。
この導入に伴い、新たに女性を中心とした営業職員が大量に採用され、家庭訪問という活動が女性に向いていたこと、また戦争復興期で男性が求人難であったことが理由と言われています。
そして、今日の「保険外交員」のベースが出来上がっていったのです。
2005.7.31記事 2007.7更新 |