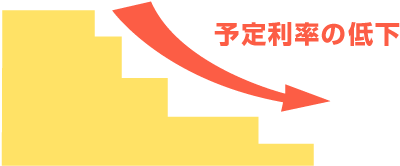ファイナンシャルプランナーのかづな先生が生命保険の歴史を解説するページです。 |
|||||||||||||
|
|
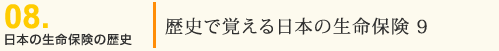
バブル期に5.5%をつけたこともある予定利率は、現在は1.5%〜1.65%と低水準で推移しています。バブル期に圧倒的な販売力を誇った郵便局の簡易保険に対抗して、民間の生命保険会社は予定利率を引き上げ過ぎたことが最大の原因であり、バブル崩壊後は予定利率をどんどん引き下げて、料率改定を行いました。
予定利率の引き下げを段階的に実施したために、個人年金保険・養老保険などの貯蓄系商品について保険料が上がり、相対的に商品の魅力が低下していったのです。 バブルの絶頂期のときに終身保険を販売していたときは、各生命保険会社はここまで金利が低くなるとは想定していませんでした。 投資している株式に巨額の含み益がある間は、株式を売却すれば簡単に穴埋めすることができましたが、株式市場の下落・低迷が続いたため、含み益もあまり出ず、なんとか予定死亡率から発生する「死差益」や「予定事業比率」から発生する「費差益」のプラスでカバーするようにしていました。 このように、赤字が大きくなりすぎると、保険金や解約返戻金を支払う目処がたたなくなる事態がおこります。 2005.9.4記事 2007.7更新 |
||||||||||||
|
Copyright(C) 2002-2014 Felice Plan, Inc. All Right Reserved.
|
|||||||||||||