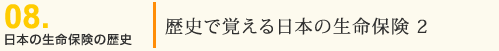
明治生命、帝国生命、日本生命の3社が業務の拡張に努めた結果、これら3社の業績が向上してきたこともあり、各地の資産家達が生命保険事業に注目し始めました。
明治25年、26年頃から事業意欲を多分に伴った株式制度の生命保険会社が各地に濫設されるに至りました。
この動きは、明治27年をピークに、明治31年、32年頃まで続きましたが、この間に新設された会社は40数社(株式会社)にも及び、さらに全国各地で類似事業が行われて、その数は数百にのぼりました。
その多くの会社が統計的基礎を欠く保険事業であったり、競争の激化で無理募集や義理募集を行ったこともあって、生命保険会社に対する非難が沸き起こりました。
当時の新聞には、生命保険事業を批判する記事が数多く見られるようにもなりました。
こういった状況の中で、業界内から、このような状況を放置することは、正しい生命保険事業の発達を妨げるものであるという声が起こり、その結果明治31年に業界が協力して、生命保険事業の正しい発展と秩序を保つために現在の生命保険協会の前身である生命保険会社談話会を設立したのです。また、明治32年には、保険数理の専門家達によって日本アクチュアリー会が設立されました。
また、政府としても、より厳しく保険事業の取り締まりを行い、監督を強化すべきであるという意見が出てきました。
そこで、明治32年に、ドイツの保険監督法に範を取り、保険業法が制定され、農商務省に商工局保険課が新設されて、保険事業の監督行政が行われるようになりました。
この業法の制定に当たっては、当時日本生命の社医を辞していた矢野恒太(のちの第一生命の創立者)の多大な貢献があったのです。
保険業法の制定によって、その後類似会社の濫説はあとを絶ちました。
また株式会社組織の他に、相互会社組織による生命保険会社の設立が認められるとともに、事業方法書や普通保険約款を統一整備する必要が生じました。
従来の約款は各社まちまちでしたが、業法の制定により統一約款を定めたいという各社の要望に沿って、生命保険会社談話会では、明治33年にわが国で最初の模範普通保険約款を制定しました。
さらに、業法の制定により相互会社の設立が認められたので、明治生命・帝国生命・日本生命に続き、第4番目は、明治35年に第一生命、第5番目は、明治37年に千代田生命(現在はAIGスター生命)の2社が相互会社として設立されました。
明治27年の日清戦争、明治37年の日露戦争を通じて、生命保険の被保険者の中で数多くの戦死者が出ましたが、生命保険会社はこれらの遺族に対して、保険金を支払いました。
その結果、多くの人々に生命保険の効用について理解を得ることができたのです。
日露戦争後、日本経済は活況をとりもどし、また一般の人々にも生命保険による経済準備の必要性が序々に認識され、新規加入者も順調に伸展していきました。
明治44年には、明治生命・帝国生命・日本生命の3社がこれまでの被保険者の死亡率を基にした死亡表「日本三会社生命表」を作成しました。
これは、わが国最初の経験死亡表であり、それまで明治・帝国生命などが使っていた「英国17会社表」、日本生命が使っていた「藤原氏表」と比べ、実際の死亡率に近いものでした。
2005.7.17記事 2007.7更新 |