ファイナンシャルプランナーのかづな先生が生命保険の歴史を解説するページです。 |
|||||||||||||
|
|
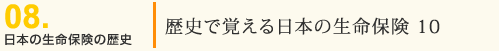
長引く不況と低金利状態のなかで、生命保険業界は大きな転換期を迎えました。この頃からそれぞれの保険会社が独自性を発揮し、積極的な商品開発を推進していったのです。 まずは、保険料率に対して2つの制度が導入されました。 5年ごと配当型商品の発売保険料を従来の有配当商品よりも割安にするために、有配当商品、無配当商品の他に、5年ごとに利差配当のみを分配する商品を発売。 高額割引料率の導入保険金額が一定の水準を超えた場合に、保険料を割り引く制度。 この2つの制度がきっかけとなり、平成11年の料率改定より各社が戦略的な料率設定の色彩が強まり、さらにいろいろな制度や商品を開発していきました。 保険料払込免除特約三大疾病、一定の要介護、一定の身体障害の場合に以後の保険料を不要とする特約。 家計を支えていた者ががんなどにかかった場合、収入が減少するケースが大半。従来の保険では、がんなどを支払事由として特約の給付金を受け取った場合でも、保険を継続していくためには、保険料の継続的な払込が必要でした。この特約を付加することにより、以後の保険料が免除されるというもの。ただし保険料払込免除がなくとも一定の身体障害の場合は払込免除になるのが普通であり、ここでの特約とは保険料免除の条件が大幅に緩くなる特約のことです。 契約者単位の通算割引契約者単位で契約を通算し、その合計の保険金額で高額割引を行う仕組み。 割引の方法としては、2つ。
更に、同一契約者のみでなく、配偶者を契約者とする契約についても、通算に加えている会社もあります。 低解約返戻金型商品解約返戻金額を低く抑えたり、全くなくすことにより、保険料を割安にした保険。 優良体保険従来の引き受け基準に、さらに厳しい引受条件を加えた「優良体」という基準を設け、それに該当する被保険者は、割安な保険料で保障を得ることができる保険。 アカウント型商品
貯蓄機能のある積立口座に、死亡や医療の保障を組み合わせた保険。正式名称は利率変動型積立終身保険。 平成17年(2005年)に発覚した明治安田生命保険による死亡保険金の不当な不払いが発端となり、保険業界全体の保険金不払い問題が社会問題に発展。 手術給付金の保障範囲の拡大
基本的に健康保険が適用される手術はすべて給付対象になる制度。 引受基準緩和型
加入時に医師による診査がなく、健康状態について告知する項目も通常より少ないタイプの保険。 平成19年(2007年)になると、医療保険が、長く生保商品の代表格だった定期付終身保険を契約件数で初めて上回りました。生保商品の主役が交代したのです。 また、平成22年(2010年)では、長期金利の低下で終身保険の高い予定利率が維持できず、販売を休止したり、予定利率を見直す保険会社も相次ぐ時代となりました。 2005.9.11記事 2011.3更新 |
||||||||||||
|
Copyright(C) 2002-2014 Felice Plan, Inc. All Right Reserved.
|
|||||||||||||
