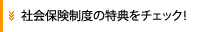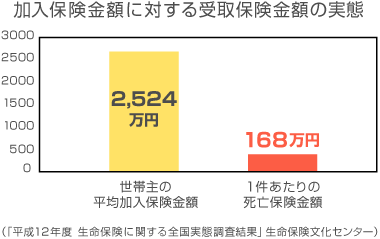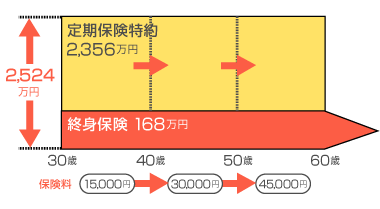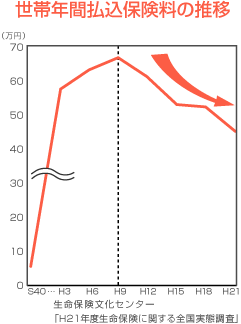ファイナンシャルプランナーのかづな先生による生命保険選びに役立つページです。 |
|||||||||||||
|
|
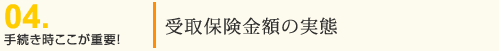
「みんなどんな生命保険に入っているの?」で勉強したように、平成21年度生命保険文化センター調べによると、世帯主の方の平均加入保険金額は1,768万円。
人は必ず亡くなりますので、いつ亡くなっても、この2,524万円の保険に加入していれば、2,524万円がもらえるはずですが、実際はそうではありません。
保険加入をしたときに、「いくらくらいだったら払えますか?」と質問されて、「1万5,000円くらいかなぁ」と漠然と答えたために、「みなさんもだいたい同じようなプランですよ。」というセールストークにのって、内容も見ずに契約をしてしまったという経験はありませんか? 上記の例であげている保障図は、そのようなケースで加入した場合の保険のしくみです。 「更新しないと、168万円の死亡保障になります。」と説明されて、特に子供がいる方は、そのような保障額では困るということで、保険料が2倍になっても継続していきます。 60歳で亡くなる方の割合は、100人中約5,6人と言われていますので、大多数の方が60歳以降に亡くなる確率が高いということで、実際に受け取る保険金額が168万円ということは納得できます。
総務省統計局「家計調査」によると、給与所得は右肩上がりではなく、年々減少しています。 しかし、保険料のことばかり気にして、万が一のときの必要保障額が不足していた、ということでは、保険の役割を果たすことはできません。
2004.9.5記事 2011.3更新 |
||||||||||||
|
Copyright(C) 2002-2014 Felice Plan, Inc. All Right Reserved.
|
|||||||||||||