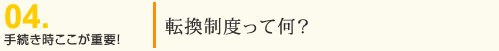
転換制度とは、現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として、新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。
転換制度
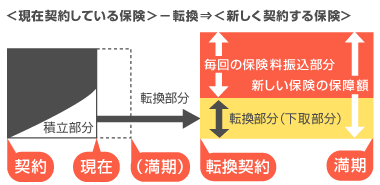
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。
主契約と特約の組み合わせやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更することができます。これらの内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得した上で契約することが大切です。
- 同じ生命保険会社でなければ利用できません。
- 転換制度の利用時の年齢・保険料率により保険料を計算します。
- 転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、
保険種類によっては保険料が引き上げとなります。
- 告知(または診査)が必要です。
- 元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。
- 生命保険会社によって取扱基準が異なります。また、転換制度を
取り扱わない会社もあります。
- 新規に契約する場合と同様の要件でクーリング・オフ制度の適用を
申し出ることができます。
転換制度の利用をすすめる場合、生命保険会社は、転換以外の方法や転換した場合の新旧契約の内容比較について、書面を用いて説明することになっています。その内容を十分理解し、納得した上で契約しましょう。
すでに加入している保険には、責任準備金や配当金などが積み立てられているので、そのお金を頭金に使って、新しい保険に加入すれば、割安な保険料で、より大きな保障を買えるということで、転換後の新しい保険商品の方が有利に見えます。通常、更新時の場合、その時の年齢・保険料率によって保険料を計算しますので、同じ保障額を継続するには、当然保険料が高くなるはずですが、アップする部分に、転換制度を使って今までの積み立てた部分を当てれば、保険料がアップするのをおさえることができるからです。
しかし、確認しなくてはいけないことは3点あります。
1. 貯蓄性を兼ねて加入していた終身保険は、貯蓄性部分を新しい保険の掛け捨てにあててしまうことによって、貯蓄性が薄れる場合があります。
2. 予定利率は、転換時の予定利率が適用されるため、高い予定利率を失ってしまいます。
3. 割安な保険料で、より大きな保障を買えるのが魅力としても、果たして、これ以上の死亡保険金額が自分にとって必要でしょうか?
転換制度といっても「基本転換」、「定特転換」、「比例転換」の3つのタイプがあります。
どの方式を選ぶかによって、払込保険料に差が生じますので、気をつけましょう。
転換価格を終身保険のみに充当する方式です。
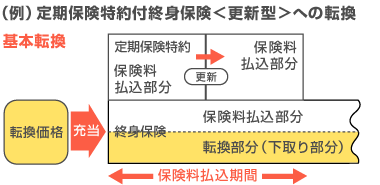
- 終身保険の保険料負担が軽減されます。
定期保険特約の保険料負担は軽減されません。
転換価格を定期保険特約のみに充当する方式です。
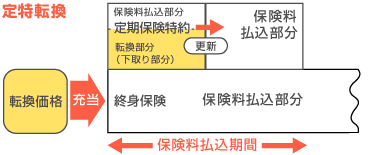
- 保険料負担が軽減されるのは定期保険特約のみです。
終身保険の保険料負担は軽減されません。
- 定期保険特約が更新をむかえると、定期保険特約の
保険料負担は軽減されません。
転換価格を一定の割合で分割し、終身保険と定期保険特約のそれぞれに
充当する方式です。
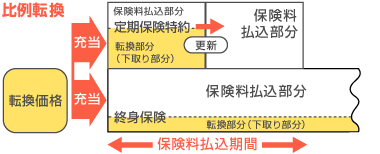
- 終身保険・定期保険特約それぞれについて、保険料負担が軽減されます。
- 定期保険特約が更新をむかえると、保険料負担が軽減されるのは
終身保険のみになります。
上記以外に、転換価格を新しい契約の保険料の一部として充当する方式をとる生命保険会社もあります。
※定期保険特約付終身保険を同種の保険に転換する場合には、定期保険特約が全期型になるのか更新型になるのかについても確認しましょう。
<定特転換>は、割安な保険料で高い保険金額が必要になったという、お子様が生まれた場合などに有効ですが、貯蓄性は全くなくなってしまうことになります。次回の更新時に、同じ保障をもつのであれば、保険料がアップしてしまいますので、10年後は、保険に頼らなくても大丈夫というライフスタイルを目指さないと、お子様の教育費もかかる頃に、保険料がアップするというダブルパンチに遭遇することになってしまいます。
生命保険会社が転換制度をすすめたがるには、次の理由が考えられます。
1. 予定利率の高い保険を継続されると、保険会社の負担が大きいため、予定利率の低い新しい商品に切り替えてもらうと、保険会社の財務内容向上に貢献度アップにつながります。
2. 保障額の大きな保険のほうが、成績の評価が上がり、保険販売員の収入アップにつながります。
最近は、この意図を汲み取られないように、転換を「コンバージョン」と呼ぶ場合もあります。転換を英語で表現すると、「コンバージョン」。表現は違いますが、制度の内容は一緒です。
2005.10.9記事 2007.7更新 |