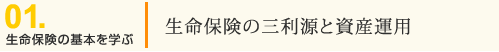
契約者から集めた保険料は、共有の準備財産として生命保険会社が管理して、運用しつつ、健康状態の悪い人が加入して、全体の死亡率を悪化させることのないように、また、より安全・確実・有利に運用するように、制度運営の経費を少しでも切りつめるなどといった経営努力を払い、保険会社は利益を出しているのです。
生命保険の利益は、「死差益」「利差益」「費差益」の3つから成り立っています。
死差益
予定死亡率によって見込まれた死亡者数よりも、実際の死亡者数が少ない場合に、生ずる利益。
つまり、あらかじめ予定していたよりも保険金の支払いが少なかった場合に出る利益のことです。
日本のような安定した社会では、死亡率は大体一定しているということと、保険は安定運用が原則であるため保険会社は死亡率を高めに設定しています。
よって、保険会社は常に死差益が生じるようになっています。
医療保険の場合は、死差益とはいいませんが、同様に疾病率の差から利益が生まれます。
利差益
予定利率によって見込まれた運用収入よりも、実際の運用収入が多い場合に生ずる利益。
つまり、あらかじめ予定していた運用利回り(予定利率)より運用成績が良かった場合です。
この場合は、運用成績と予定利率の差がそのまま利益となります。
費差益
予定事業率によって見込まれた事業費よりも、実際の事業費が少なくてすんだ場合に生ずる利益。
つまり、あらかじめ差し引いた経費よりも実際の運用コストが低い場合に生じる利益のことです。
いくら死差益や費差益で利益が出たとしても、長引く低金利や株安によって、保険会社の運用成績は悪化し、利差益どころか、運用成績が予定利率まで達成しない「利差損」が発生しています。
この差損の生じている状態を「逆ざや」といいます。
それでは、保険会社はどのように保険料を運用しているのでしょう。
資産運用の原則は4つから成り立っています。
「安全性」
運用される資産は、将来保険金として支払われるものなので、将来の支払いに支障がないように安全に運用します。
「収益性」
保険料は、予定利率であらかじめ割り引かれていますので、予定利率以上に運用することが必要です。
さらに、配当金の割り当てを多くし、契約者の保険料の負担を軽減するために常に収益性を考えながら運用しています。
「換金性(流動性)」
保険金の支払いが集中した場合に備えて、また機動的な運用ができるように、資産の一部を換金性(流動性)のある預貯金や公社債などで保有しています。
「公共性」
資産は多くの契約者から払い込まれた保険料をもとに成り立つものですから、国民経済や生活の向上に役立つような公共性をもった運用をしています。
資産の利用方法や利用割合などについての具体的なことがらは、内閣府令で定められています。
資産運用は主に3つで行っています。
「有価証券」
有価証券としては、株式・公社債・外国有価証券などで運用しています。
「貸付金」
有担保を原則として貸し出しされており、貸付先は、基幹産業や国民生活に関わりの深い産業など幅広い分野にわたり、中小企業貸付や住宅ローンなども行っています。
注:約款にもとづいて、契約者貸付や(自動)振替貸付も行われています。
「不動産」
土地・建物などの不動産は、自社の営業用のものと投資用のものに分けられ、海外の不動産にも投資しています。
2005.12.8記事 2007.7更新 |