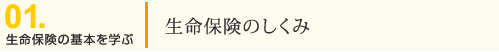
前回は、生命保険の必要性についてお話しました。
「将来の不安に備えるために」ですが、保険は晴れた日に傘を買うようなものであり、何かが起こってからでは手遅れなのです。その将来のあらゆるリスクに備え、保険会社はいろいろな保険商品を販売しています。
今回のゼミのテーマは、生命保険の基本的なしくみについてです。
人間は昔から集落生活や大家族の中で、危険にあって不幸になった者をお互いに助け合うという共同保障の工夫をしてきました。
しかし、産業が発達し、社会的分業が行われるようになり、家族生活の単位が小さくなってくると、一家の主な収入を得ている者が死亡した場合、残された家族の生活への影響はかつてないほど大きくなってきました。
そこで考え出されたのが、相互扶助の理念によって助け合う生命保険のしくみです。
日本では、慶応3年(西暦1867年)、福沢諭吉が「西洋旅案内」でヨーロッパの近代的保険制度を紹介したことが発端になり、明治時代に入って生命保険会社が設立されました。
生命保険はこのように、お互いに助け合う「相互扶助の精神」が基本となっているため、保険会社も相互会社形式でスタートした会社が多くなっています。
相互会社とは、契約者が社員(出資者)となり、会社の利益は社員に還元するというもので、利益を徹底的に追求し、利益を株主に還元する株式会社とは、会社の性格が大きく異なります。
保険会社が契約者からお金を集め、それを株式・債券・貸付・不動産などに投資をして運用し、その運用利益などで会社の諸経費をまかなうとともに、契約者に万が一のことがあった場合に、保険金や給付金を支払います。
また、保険が満期になった場合には満期保険金などを支払うしくみになっています。
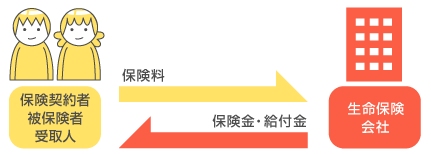
2004.1.25記事 2007.7更新 |