ファイナンシャルプランナーのかづな先生が生命保険と税金を解説するページです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
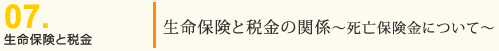
死亡保険金を受け取った場合にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人が誰であるかによって、税金の種類が異なってきます。 では、契約形態の違いによって、どのような税金がかかるかをみてみましょう。
相続税:相続人が受け取った場合<保険金非課税の特典有>契約者と被保険者が同一人の場合の死亡保険金を、被保険者の相続人が受け取った場合は、相続税の課税対象となります。 相続税の課税対象額
(500万円×法定相続人の数)を超えた額 相続税:相続人以外の人が受け取った場合<保険金非課税の特典無>死亡保険金を被保険者の相続人以外の者が受け取った場合は、遺贈によってもらったものとみなされ、相続税の課税対象となりますが、この場合には非課税の特典はありません。 所得税:契約者と受取人が同じ場合契約者と受取人が同じ場合の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。 所得税の課税対象額
{死亡保険金額−支払った保険料−50万円(特別控除)}×1/2 この金額を、他の所得と合算して、総合課税の対象となります。 贈与税:契約者、被保険者、受取人が違う場合契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。 贈与税の課税対象額
死亡保険金額−110万円(基礎控除) 贈与額は、保険金のほか同年中に受けたすべての贈与が含まれます。
2005.1.30記事 2007.7更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright(C) 2002-2014 Felice Plan, Inc. All Right Reserved.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

