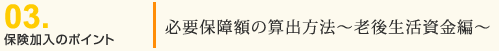
一般的に定年退職の年齢は60歳、そして15歳〜64歳までを生産年齢人口と区別しているため、65歳以上が老後の生活もしくは、セカンドライフと言われています。
平均寿命が世界トップクラスの日本においては、死ぬリスクよりも、生き長らえるリスクが切実な問題となっています。60歳で退職し、80歳まで生きると仮定すると、20年間。
退職前と退職後で毎月の生活費が大きく変わらないとすると、生活費が30万円かかっている場合、毎年360万円、20年間で7,200万円も老後の生活費が必要となってきます。
このお金を準備できるか、できないかが「かわいいおばあちゃん」「すてきな老紳士」となるか、「みじめな老人」になるかの分かれ目になるのです。
準備のために「いくら払えるか」ではなく、「老後の資金としていくら用意しなくてはいけないのか?」という必要保障額を知った上で、自助努力していくことが重要です。
必要保障額は一人一人違いますが、今回は夫婦2人で定年後に生活していく場合の必要保障額の算出方法を勉強します。自助努力により準備すべき老後資金の一般的な算出方法は、夫婦2人の期間と妻1人の期間の生活資金に別途必要資金を加えた総額から、公的年金(老齢年金など)、退職一時金・年金や預貯金などの自己資産を差し引いて計算する方法です。
必要保障額は2つの期間を合わせて考える必要があります。
前半は、夫婦2人で過ごす期間の生活費、後半は妻1人の期間の生活費です。
これは、夫婦年齢差、および男女の平均寿命の違いにより、一般的には夫の死亡後、妻1人で生活しなければならない期間があるためです。
それでは、さっそく5つのステップを勉強していきましょう。(これから解説する5つのステップは算出方法の一例ですので、他にも違う算出方法があります。)
現役時代の生活水準をもとに、夫の定年後から夫が死亡するまでの夫婦2人で過ごす期間の生活資金としてどの程度必要とするかを見積もります。
この期間は、現役時代の生活費の70%を目安とします。
STEP1:夫婦2人で過ごす生活資金の計算…A
●現在の1年間の生活費×(夫の平均寿命−定年退職の年齢)
⇒ 通常、夫の平均寿命は79歳とします。
夫死亡後、妻が1人で平均余命まで生活する期間は、現役時代の生活費の50%を目安とします。
STEP2:妻1人で過ごす生活資金の計算…B
●現在の1年間の生活費×(妻の平均寿命−夫死亡時の妻年齢)
⇒通常、妻の平均寿命は86歳とします。
STEP3:別途必要資金の計算…C
住宅ローンの残高、住宅のリフォーム資金、家賃(賃貸の場合)、レジャーや余暇活動のための資金、子どもがまだ結婚していない場合は結婚資金の援助金、病気やケガなどに備えての予備費、など生活資金以外で別途まとまって必要になる資金を見積もります。
STEP4:収入見込み…D+E+F
公的年金、退職一時金・年金、預貯金などの収入を見積もります。
●社会保障(公的年金) ・・・D
●企業保障(サラリーマンの場合、退職一時金・年金など) ・・・E
●自己資産(預貯金・有価証券・売却可能資産など) ・・・F
STEP1からSTPE4までの各数値から必要保障額を算出します。
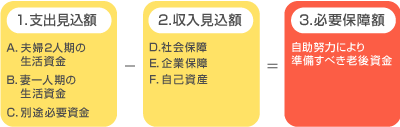
老後生活資金のベースとなるのは、やはり公的年金ですが、サラリーマンの場合と自営業者の場合とはSTEP4の収入見込み額が違ってきますので、職業によって自助努力による準備資金が大幅に変わってきます。
また、公的年金制度は5年に1度制度の見直しを行うことになっていますので、公的年金に全面的に頼って準備資金を用意することは、これからの時代は危険です。
自助努力のウエイトはこれまで以上に高まってくるということを考慮にいれて、プランニングしていくことが重要です。
2004.9.26記事 2011.3更新 |